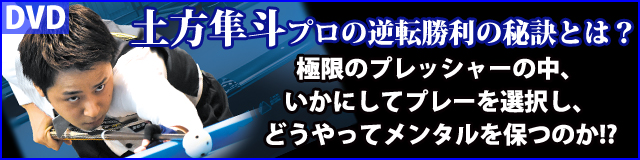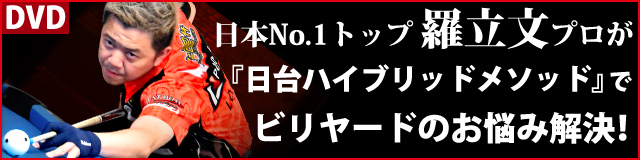Chapter10 Rai Takagami

作/Donato La Bella 文/渡部嵩大 監修/関浩一
第10話
強風と雷鳴の中、現れた人影の正体は翔の兄、鷹上雷(たかがみ・らい)だった。突然の不気味な天気のことも忘れ、兄との久しぶりの再会を喜び翔は駆け寄ったが、雷は弟には目もくれず、父親である明の目を見据えながら真っ直ぐと歩み寄った。明は雷の様子がおかしいことに気が付き、奥で2人で話そうと告げた。のんきな翔でさえも、この物々しい雰囲気は感じ取っていた。

風のエレメントを操り、いつも陽気な性格を持つ弟とは対照的に、どこまでも自分を追い込むような性格を雷は持っていた。鷹上家の長男であるということも彼の中の責任感やプライドを作り上げ、自然の成り行きとして彼は火のエレメントを習得していた。
明と雷は道場の隅の部屋に入っていった。そこには明が現役時代に手に入れた、無数のトロフィーや賞状が飾られていた。雷にとっては昔から見慣れていたものだった。
「修行を成し遂げたのか、雷」
重い沈黙を破り、ついに明が話を切り出した。少しの間をおいて、雷は含み笑いをしながら
「なぜ聞くまでもない質問をするんだ。まさか俺にできないとでも思っていたのか」
と修行前とは大きく変わった調子で語り始めた。そうしているうちに雷の両目は黒く染まり、背後に黒い影がうずまき始めた。その様子に恐れおののく明を見て、雷は笑いを浮かべながら続けた。

「そうか、親父には見えるのか、この力が。今の俺の強さがわかっただろう。俺は誰も到達したことのないレベルにまで行き着いた。身を粉にして自力でつかみ取ったんだ。俺がビリヤードの新しい時代を築き上げる! 世界はこの力を求めている!」

「なんということだ、雷。お前はその力を得るために、何を犠牲にしてきたかわかっているのか。もう十分だ。しばらくはビリヤードから離れるんだ」
「何をバカなことを言ってるんだ。親父の成し遂げられなかったことを、俺は鷹上の血を引く者として責任を持ってやり遂げたんだ。ここまでして手に入れたものを手放す訳がない。だから親父は甘いんだ! 鷹上の名はこの俺がしっかりと継承してみせる」
明の目は、およそ息子に向けられる父親のものではなかった。恐怖とも、失望とも読める表情を浮かべていた。雷は父親に背中を向け、振り返ることなく
「わかった。俺は俺の道を行く」
と最後に言い残すと、部屋を後にした。
翔、龍、すみれの3人は道場の前で立ちつくしていた。雷と明の話はよく聞こえなかったが、声のトーンや雰囲気から何か良くないものを感じ取っていた。そこへ、道場の中から雷が現れた。3人が何も言えずにいると、急に雷は翔に向かって、
「お前のような弱いやつが鷹上を名乗る資格はない」
と言い放った。友を侮辱された龍は一瞬で頭に血が上り、雷に飛びかからんとする勢いだったが、翔がそれを制した。
「いいんだよ、龍。俺がまだ弱いっていうのは本当のことだからな。でも雷、次に会った時には俺は負けない」
それを聞き、雷は高らかに笑った。影が揺れ始めた。
「ははは、そうかそうか。修行の本当の厳しさをお前は知らない。やれるものならやってみるがいい」

その言葉を最後に、雷は道場を去ってしまった。黒い影を背負って。
憔悴しきった様子で、明は姿が見えなくなるまで雷をじっと見つめていた。その様子に気が付くと、3人は明に駆け寄った。
「なんということだ。私はどこで間違えてしまったのだろう。私は……」
嵐のように雷が現れて立ち去った後には、ただ静かな道場がたたずんでいた。
快晴の広がる北の大地では、ケヴィンがビリヤードテーブルの横でチェスの駒をいじっていた。ケヴィンと雫は精神を鍛えるために瞑想を取り入れていたが、チェスも同様にケヴィンにとっては集中力や戦略的思考を鍛えるのに一役買っていた。もっとも、雫はチェスに関してはさっぱりで、いつもケヴィンの話を聞き流していた。
「なあ雫、知ってるか? チェスでは一度だけ、同時に2つの駒を動かすことが許されてるんだ。これをキャスリングと言って、つまり王の入城ということだな。キングを守りながら、ルークを攻めの駒として活躍させることができる。なんだかビリヤードのセーフティに似ていると思わないかい? セーフティは守りとしての手段のように見えるが、その実、攻めと守りは表裏一体だ。相手を攻める最高の手段にもなり得る。……雫、聞いてるか?」
「ねえケヴィン、今度の北海道オープンの出場者リストなんだけど、これ見て。鷹上雷。この間の鷹上くんと何か関係あるかもしれないね」
「ん、ああ、そうかもしれない。万全の体制で本番を迎えないとな」